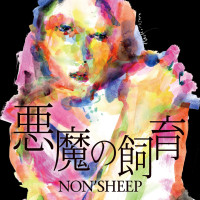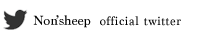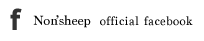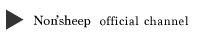佐藤雄駿×中村文則 対談
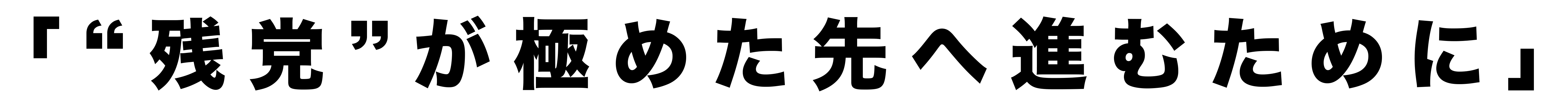

芥川賞作家の中村文則さん――。ノンシープ・佐藤は、純文学界のヒットメーカーとして知られる稀代の作家を尊敬し、交流を続けてきた。お互いに今年が15周年という共通点もあり、今回、特別対談が実現したのだが……。「俺の話はいいんだよ!」と言いながら、佐藤を追及(?)する「文則さん」の優しさと熱さが胸に沁みる対談となった。「共に生きましょう」は中村作品の読者にとっておなじみのフレーズだが、その言葉が実体を伴って浮かび上がってくる、そんな会話が繰り広げられた。
言いたいことがあって来た
中村:佐藤くんは、今、いくつになったんだっけ?
佐藤:33歳です。
中村:もう33歳か。20代のような気がしていた。俺が40だから、そうか、佐藤くんも歳を重ねるわけだよね(笑)。出会いは、ノンシープが『遺書』を出す直前。佐藤くんの手紙と一緒に、当時、ノンシープが所属していた事務所から「ライナーノーツを書いてくれないか」だったか「会いませんか」だったか、そんな依頼があって。あれは2009年? で、今は自分たちでマネージメントもすべてやっているんでしょう?
佐藤:そうですね。僕は『何もかも憂鬱な夜に』を読んで衝撃を受け、思わずファンレターを書いたんです。それを事務所から送ってもらった気がします。
中村:時々、ライナーノーツの依頼はある。でも、本当に良いと思わないと書けないでしょ。『遺書』はすごく良かった。歌詞が暗くて、変わっていて面白いと思った。それと、佐藤くんの手紙がすごく下手な敬語で書かれていたのが印象的で(笑)。ああ、敬語を使い慣れていない人が頑張って書いてくれたんだなあ、きっと素直な人なんだろうなあ、と思ったんだよね。
佐藤:うわあ、なんかすみません……。

「自分たちの世界観ややりたいことを深堀りし続けていますけど、それだけでいいのか、いいわけない、とは思っているんです」
中村:それから時々、会うようになった。でも、今日は久しぶりだよね。3、4年ぶりになるのかな? 作家の生活って結構忙しいから、すぐに時間が過ぎてしまって、久しぶりの気がしないけれど、まずは佐藤くんの顔色が良くなっていて良かったよ。
佐藤:えっ? そうですか?
中村:すごく痩せて元気がなかった時があったじゃない。俺、心配になって、体調を聞いた気がする。
佐藤:ああ、そんな時期がありました。でも、今日は文則さんの顔色が悪いですよ?
中村:俺は単に忙しくて疲れているだけだから、大丈夫(笑)。
佐藤:そんな忙しいなか、時間を作ってくださって、ありがとうございます。
中村:そうだよ、今日はどうしても言いたいことがあるから、来た。
佐藤:言いたいこと……?
中村:新曲の『残党』をきちんと聴かせてもらった。歌詞もじっくり読んだ。すごく良い曲だったよ。俺は音楽の素人であくまでも聴き手としての感想だけど、こうしたオーソドックスな方向性のJ-ROCKの完成形と言ってもいいんじゃないかな。
佐藤:完成形って。深堀りはしましたけど、それは言い過ぎですよ。
中村:いや、たぶん、この手のジャンルでこれ以上のものはないんじゃないかな。ノンシープが演っている方向性で極められた完成形だと思う。15年間の集大成として素晴らしい楽曲。だけど、俺が少し引っかかるのは、その曲のタイトルが『残党』だったこと。残党って言うからには、鬱積した何かを抱えているってことだよね?
佐藤:ううう、文則さんとお会いする時の感じを思い出してきました。いつも叱咤激励されるという。
中村:俺もなんだかデジャブみたいなんだけどさ(笑)。
佐藤:ですよね(笑)。やるべきことはやっているけれど、思ったように転がっていかないという気持ちは当然、持っています。
中村:そうでなければ『残党』なんて言わないよ。俺はね、「なんだよ残党って。それなら、もっと積極的に売り込めよ。レコード会社に入れよ。ノンシープとはこれだ!という曲を持って、俺たちをなんとかしろ!って押し掛けろよ」と思ったの。だって、ずっと待っていたから。メジャーに所属するとか、なんらかの「僕たち、こうなりました」という報告を。でも、来なかった。だから、15周年のお知らせをもらって、「ずっと待っていた」ことを直接伝えようと思った。対談を断ることも、「新曲、良かったよ」とだけ伝えてお茶を濁すこともできる。でも、俺は今日こうして佐藤くんに会いに来た。それだけ、ノンシープはすごくいいバンドなんだから、もっと売れてほしいと思っているんだよ。今、音楽業界が難しい状況で、そう簡単な話じゃないとわかってはいるんだけど。

「自分の核はそのままで、常に発展させようとしている」
「大きな表現者」になるために
佐藤:おっしゃってくださることはよくわかります。僕たちもやりたいこと、出来ることを懸命に深堀りしながら、今後どう転がしていけばいいか、考え続けているので。
中村:小説で言うと、たとえば太宰治のように、若い時に特に響く作品があるじゃない? 今のノンシープもそんな感じがする。そういう音楽って、とても尊い。だからこそ、何か少し新しい要素を取り入れてさらに進化させてほしいと思った。
佐藤:同じことをやり続けている自覚はありますが、僕たちは開き直って掘り下げる方向に向かったんですよね。
中村:そうだったのか。自分たちの核を大切にして掘り下げるのは良いことだよ。一方で、閉鎖的になる面はないのかな。
佐藤:バランスがなかなか難しいです。その点、文則さんの作品は新しい要素がどんどん加わって、大きく変わってきているように思うんですが、どのように変化を生み出しているんですか?
中村:ノンシープの話をしに来たんだから、俺の話はいいんだよ。
佐藤:そう言わずに、ぜひ教えてください。
中村:核は同じだけど、新しいことにもチャレンジしてるよ。たとえば『教団X』には色々と新しい要素があるけど、手記や告白の部分では、デビュー当時の『銃』や『遮光』の感覚がそのままある。だから、中村は変化したとたまに言われることもあるけど、核は変わってないの。もし俺がどこかで急変していたら、文学の世界にもういなかったと思う。とっくに消えていたはず。逆にずっと同じことを続けていても、消えていたと思う。初期の『銃』や『遮光』が今も売れ続けているのは、新しい作品の俺の芯を気に入ってくれた読者さんが遡ってくれているからなんだよ。25歳でデビューして、今、40歳。ずいぶん歳をとった気がするけれど、作家だと40歳はまだ若い。だから、今後の長いキャリアの中で、今のうちにいろんなやり方でやっておきたい。でも、昔あの物語を書いたから今の物語がある、というブレない芯は持ち続けるべきだと思っている。
佐藤:なるほど。僕たちはやりたいことを誰にも介入されずに追求していますが、その中で、なかなか評価されないことに意地になり、変化が足りない面があるかもしれません。
中村:わかるよ。それはすごくよくわかる。芯を追求し続けるのはとても良いと思う。ただ、同時に幅を広げることも大事じゃない? 映画監督のフェデリコ・フェリーニの言葉だった気がするけれど、「自分のやりたいことをやるのは簡単だ。自分のやりたいことを社会に広げるのが難しい」みたいな言葉がある。俺はチャレンジするのが好きで、かつ、自分の「好き」の範囲が比較的広かったのは運が良かったかもしれない。いずれにせよ、本気で大きくなりたいと思うなら、違う方向性の新しい風を入れてみたらどうかなあ。それがレコード会社かプロデューサーかマネージャーか、わからないけれど。って、なぜ中村文則がミュージシャンに説教しているんだ、って思われるね(笑)。
佐藤:ははははは。文則さんの変化とブレない理由がわかりました。
中村:能力を上げるには新しいチャレンジをして成長し続けるしかないから。
佐藤:それは、確かに。
中村:「大きな表現者」になるためには、それしかないと思う。
佐藤:「大きな表現者」。すごい言葉が出てきた。大きな表現者、か……。
「ミュージシャンは独特で特別な憧れの職業。残党にすらなれなかった人たちが多いなかで、ノンシープは残党として生き残っているんだから、良い方向に行ってほしいんだよ」(中村さん)
「が、頑張ります……!」(佐藤)
中村文則とノンシープの共通点は「暗い世界観」
中村:アメリカに行くとつくづく思うんだけど、ものすごい数の作家がひしめき合っている。アメリカの作家だけじゃなくて、外国人が英語で書いたものや翻訳された作品が発表されているから、本当に自分らしさを出していかないと埋没してしまう。となると、幅を広げ、チャレンジしつつ、同時に自分らしさは絶対に死守して表現しなければならない。それで、ノンシープの重要な核というか芯は佐藤くんの歌詞だとも思うから、あえて素朴な質問をするけど、なぜあんなに歌詞が暗いの?
佐藤:えええええ、なぜ歌詞が暗いのか、かあ。うーん。改めてそう訊ねられると、答えるのが難しいですね。
中村:いや、こんな質問、俺の作品を知っている人に「おまえが言うな」って言われると思うけど(笑)。俺とノンシープの共通点は作品の世界観が暗いことだし、前から訊いてみたいと思っていたんだよ。
佐藤:明るい歌詞を書こうとチャレンジはしてみるんですけどねえ。
中村:ああ、チャレンジはしているんだ? でも、どうしても明るくならない、と。ということは、佐藤くんから自然に出てくるものなんだろうか。だから、「なぜ歌詞が暗いの?」と訊ねるのは、「なぜ顔がついているの?」と訊ねるようなものかもしれないね。もう一つ、訊ねたいんだけど、『残党』に「本心」という言葉がある。でも、歌詞の中で具体的にその本心は明かされない。本心をズバリ書く選択肢はないの?
佐藤:書いてみたら、感傷的でダサくなってしまって。いろいろ書き直し、悩んだんですが、結局、最初の歌詞に戻しました。
中村:そうか、感傷的にならずに書ければいいけれど。
佐藤:本心って、たぶん、ダサいんですよ。
中村:言いたいことはわかる。でも、人が聞きたいのはそこなんだよ。本心がダサくなるかならないかは、言葉の技術の問題だよ。佐藤くんはセンスがあるんだからできるはず。はっきり言って、俺は本心を書いてるからね。ノンシープがこのままで幸せならいいけど、幸せとは言い切れないなら、時代を待つのではなく、つかみとってほしいんだよ。残党って言うなら、じゃあ、どうするの?と言いたい。だって、残党にもなれなかった人たちがいるからね。やっぱり、ミュージシャンって独特で特別な職業だと思う。絶対的に憧れの職業だよ。俺もバンドをやってた経験があるから、15年間、ノンシープがやり続けている大変さがわかるんだ。これまで諦める同業者をたくさん見てきたでしょう。だから、次の15年間のために、残党として生き残ったからこそできる、展開を見せてほしい。
佐藤:そうですね。本心に向き合って、なりたい自分たちの姿に近づけるように、今一度、自分たちらしい幅の広げ方を探りたいですね。
中村:俺は思うんだけど、日常ってハマるもの。脳は習慣だから、同じことをやり続けてしまう。変化を試みると、日常に慣れた脳が最初は億劫がる。それでも、展開を望むなら、変わらないといけないと思っている。佐藤くんも次の15年に向けて、ちょっと考えてみてよ。ってなところで、俺は今日中に戻さないといけないゲラがあるんで、もう帰るよ!
佐藤:おっと、お疲れさまです。今日は本当にありがとうございました。
中村:じゃあ、また!
構成・中沢明子
撮影・Mami Naito
撮影協力・皇琲亭
中村文則 なかむら・ふみのり
1977年、愛知県出身。福島大学行政社会学部応用社会学科卒。コンビニのアルバイトなどを経て、02年『銃』で第34回新潮新人賞を受賞し、デビュー。04年、『遮光』で第26回野間文芸新人賞、05年、『土の中の子供』で第133回芥川龍之介賞、10年、『掏摸(スリ)』で第4回大江健三郎賞を受賞し、12年には英訳の同作品でウォールストリートジャーナル紙の年間ベスト10小説に選ばれる。14年にはアメリカで、ノワール小説に貢献した作家に送られるデイビッド・グディス賞、16年に『私の消滅』で第26回ドゥマゴ賞を受賞。近著に、40万部ベストセラーとなった『教団X』や『R帝国』がある。
『何もかも憂鬱な夜に』
『R帝国』